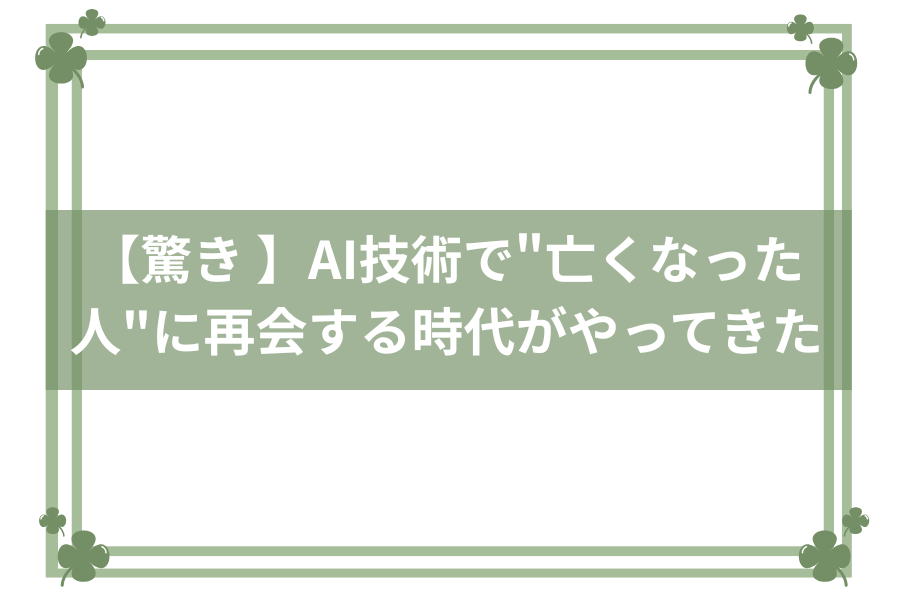SF映画のような世界が現実に
「亡くなった人とAIで”再会”する」なんて、ひと昔前はSF映画の中だけの話でした。でも今は違います。AI技術がものすごいスピードで発達して、故人の姿や声、話し方まで再現できるサービスが実際に登場しています。
写真の中のおじいちゃんが突然動き出して笑いかけてきたり、亡くなったお母さんが「元気にしてる?」と話しかけてくる。そんな体験が、もう夢物語ではなくなったんです。
今、何ができるようになったの?
昔は写真やビデオを見て思い出に浸るしかありませんでした。でも今は、AIの力で亡くなった人を「動かし」「しゃべらせる」ことができるようになっています。
実際に韓国や日本では、故人の写真・動画・音声をAIに覚え込ませて、お葬式や法要で本人の姿で挨拶してもらうサービスが始まっています。葬儀会場の大きなスクリーンに故人が映って、参列者に向かって「ありがとう、みんな元気でいてね」なんて話すんです。
見ている人たちは驚いたり、ホッとしたり、複雑な気持ちになったり。5年前なら「そんなの変だ」と言われていたことが、今では少しずつ受け入れられるようになってきています。
2019年のNHK紅白歌合戦で「AI美空ひばり」が登場した時は大きな議論になりました。でも2024年には、映画でAIが歴史上の人物を蘇らせる演出が自然に受け入れられています。人々の感じ方も、この数年でずいぶん変わってきているんですね。
どこまでリアルに再現できるの?
今のAI技術だと、故人の顔や声、身振り手振りをかなり本物らしく再現できます。SNSの投稿や手紙があれば、その人らしい話し方や口癖もAIが覚えて、会話のような形でやりとりすることもできるんです。
白黒の古い写真をカラーにしたり、写真から短い動画を作ったり、昔の映像をきれいにしたりする技術も、ここ数年でグンと良くなりました。
ただし、完全に本人と同じになることはまだできません。「なんとなく本人らしいけど、やっぱり違うなあ」と感じる人も多いでしょう。AIが覚えられるのは、残されたデータの範囲だけですからね。
将来的には、VR(バーチャルリアリティ)やAR(拡張現実)と組み合わせて、もっとリアルな”再会体験”ができるようになるかもしれません。
実際にどんなサービスがあるの?
お葬式や法要での映像メッセージ
アルファクラブ武蔵野という会社が2024年12月に始めた「Revibot」というサービスでは、故人の映像をもとに、AIが新しいメッセージを話す動画を作ってくれます。お葬式の最後に故人が感謝の言葉を述べたり、法要で家族の様子を気遣うような内容を話したりします。
スマホで故人と会話
ニュウジアの「トークメモリアルAI」では、故人の写真や動画、思い出話をもとに、スマートフォンやパソコンで実際に会話ができるサービスを提供しています。質問すると、故人が生前の話し方で答えてくれるんです。
昔の写真や動画をよみがえらせる
白黒写真をカラーにしたり、写真から動画を作ったり、古い映像をきれいにしたりするサービスも人気です。特に家族を亡くした経験がある人からは、「おじいちゃんおばあちゃんの若い頃の姿をカラーで見てみたい」という声が多く聞かれます。
でも、いろんな心配もある
AI故人の技術は素晴らしい可能性を秘めていますが、心配な点もあります。
亡くなった人の尊厳は大丈夫?
「死者の尊厳を傷つけているんじゃないか」「本人が望まない内容をAIに話させるのは適切なのか」という声があります。特に会話型のサービスでは、故人が生前に絶対言わなかったであろうことをAIが話してしまう危険性もあります。
AIに頼りすぎてしまわない?
「AIに頼りすぎて、本当の悲しみと向き合えなくなるんじゃないか」「現実の死を受け入れられなくなってしまうかも」という心理的な影響を心配する専門家もいます。
業界の取り組み
こうした心配を受けて、葬儀会社の中には専門の委員会を作って、ルールを決めて慎重にサービスを提供しているところも増えています。「AIの再現はあくまで演出で、現実ではない」ということを、利用者にしっかり理解してもらうことが大切だと言われています。
人々の気持ちはどう変わってる?
関東学院大学の折田明子先生が行った調査を見ると、人々の考え方が少しずつ変わってきていることがわかります。
2022年の調査では、「VRで故人の姿を再現したい」という人はわずか6.6%、「AIで故人と音声で会話したい」という人も4.6%と、とても少ない数字でした。
でも2025年の調査では、「ひいおじいちゃんやおばあちゃんのカラー写真をAIで作ってみたい」という人が31.8%、「声で会話してみたい」という人が10.6%と、明らかに増えています。特に、家族を亡くした経験がある人ほど、前向きに考える傾向があるそうです。
3つのレベルで考えてみよう
専門家は、AI故人の受け入れ方を3つのレベルに分けて説明しています。
- 歴史上の人物や有名人の再現:教育や娯楽として、比較的受け入れられやすい
- 既存の写真や動画をきれいにする:新しい選択肢として、徐々に受け入れられている
- 故人との会話ができるレベル:まだ慎重に議論が必要な段階
これからどうなっていくの?
技術はもっと進歩する
今はスマホやパソコンの画面での再現が中心ですが、将来的には人間のような動きをするロボットでの再現も考えられています。音声認識や会話の技術も良くなって、もっと自然な対話ができるようになるでしょう。
解決すべき問題もたくさん
一方で、なりすましや悪用を防ぐルール作り、プライバシー保護、故人の意思をどう確認するかなど、解決すべき問題もたくさんあります。特に商売として使う場合の倫理的なガイドライン作りは、業界全体で取り組む必要がある重要な課題です。
よくある質問とこたえ
AI時代の“思い出”との向き合い方
AI技術で”亡くなった人”に再会できる時代は、もうすぐそこまで来ています。これは、愛する人を失った悲しみに寄り添う新しい方法になる可能性がある一方で、「本当の死とどう向き合うか」「亡くなった人の尊厳をどう守るか」という大切な問題も私たちに投げかけています。
2019年の「AI美空ひばり」をめぐる議論から始まって、わずか数年で社会の受け止め方も変わってきました。技術の進歩は止まることなく、私たちの死生観や供養の形も変わろうとしています。
大切なのは、技術の可能性を見つめながらも、それを「どう使いたいか」「どこまで受け入れるか」を一人ひとりが真剣に考えることです。AI故人は万能の解決策ではありませんが、適切に使えば、愛する人を失った悲しみと向き合うための新しい選択肢になるかもしれません。
技術と倫理のバランスを取りながら、私たちはAIと”生と死”の新しい関係を築いていく時代を生きています。この変化をどう受け止め、どう活用していくか。それは、これからの私たち一人ひとりにかかっているのです。