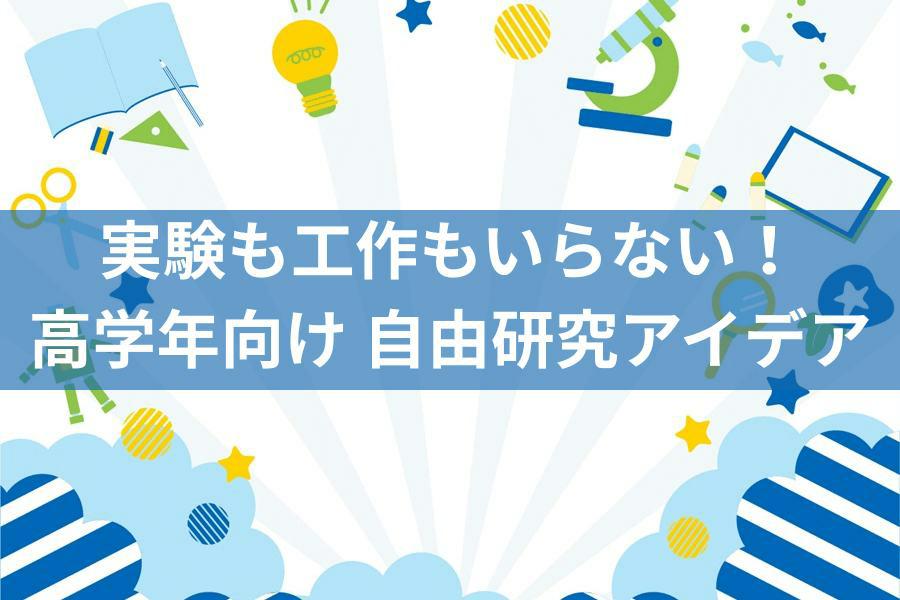「高学年の自由研究って、何かちゃんとした“すごいこと”をやらないといけないんじゃない?」
そんなふうに思ってしまうお子さん、意外と多いんです。
でも、じつは高学年こそ、「何を調べて、どう考えて、どう伝えるか」が評価される自由研究のカギなんです。
つまり、“手を動かさなくても頭を使えばOK!”なテーマがいっぱいあるということ♡
この記事では、実験や工作がちょっと苦手…という小学校高学年の子でも、自信を持って提出できる自由研究テーマを10個厳選してご紹介します!
おうちの中やネットで調べるだけでできるものばかり。
グラフにしたり、インタビューしたり、ランキングをつくったり…情報を整理してまとめる力をのばすチャンスにもなりますよ♪
この記事でわかること
- 実験・工作が苦手でも取り組める自由研究の選び方
- 高学年におすすめの「調べる・考える・まとめる」型テーマ
- それぞれのテーマの進め方とアレンジ方法
- 先生ウケする“まとめ方のコツ”
- 親が最小限サポートするだけでOKな工夫
高学年の自由研究=「調べて考える」が評価される!
小学校高学年になると、自由研究の“中身”にも少しずつレベルアップが求められますよね。
とはいえ、「すごい工作」や「本格的な実験」ばかりが評価されるわけではありません。
むしろこの学年では、
「なにを調べて、どう考えて、どうまとめたか」が評価のカギ。
つまり、“知的好奇心”と“考える力”を見せられれば、手を動かさなくても、しっかりとした自由研究になるんです。
今回ご紹介するテーマはすべて、調査・記録・分類・考察などを中心にした内容ばかり。
「理科が苦手」「絵が得意じゃない」「道具がそろわない」そんな子でも、自分らしくまとめられる自由研究になりますよ♪
実験・工作なしで選ぶときのコツとは?
高学年で“作らない系”の自由研究を選ぶときは、次の3つのポイントをおさえておくと◎です。
✅ テーマ選びのコツ
- 日常にある「不思議」や「興味」を深掘りする
→「なんでこうなってるんだろう?」を起点に! - 数字・データでまとめやすい内容を選ぶ
→ ランキング・グラフ・マップなどにしやすいテーマがGOOD! - 自分の視点や感じたことが書けるテーマ
→ 感想・考察を書けることで“研究らしさ”が出せます。
そして大事なのは、「手をかけすぎないこと」。
完璧な完成度よりも、自分の視点がちゃんと伝わるか?がポイントになりますよ♪
① 家族に聞いた!好きなごはんランキング
家族みんなに「一番好きなごはん」を聞いて、ランキングにまとめるだけで、楽しくて“研究らしい”自由研究になります!
データの集め方・表の作り方・グラフ化・感想まとめまで、高学年らしさをしっかり出せるテーマです。
✅ 進め方
- 質問を決める(例:「好きなおかずベスト3は?」)
- 家族にインタビューして記録(表にしても◎)
- 回答を集計 → 円グラフや棒グラフに!
- 「なぜその料理が人気だったのか?」を自分なりに考察
例:「お父さんは“からあげ”が1位だった。小さいころからよく食べてたからかも?」
→ こうした“仮説”を立てられると、大人っぽいまとめ方になりますよ✨
② コンビニ3社の新商品パッケージ調査
セブン・ローソン・ファミマなど、コンビニ各社の「新商品パッケージ」を比較してみる自由研究です。
デザインやキャッチコピー、色使いなどを見比べることで、「伝える工夫」や「売れる秘密」に気づけるかもしれません!
✅ 進め方
- 各コンビニで1〜2種類ずつ、新商品をピックアップ(飲み物・お菓子・パンなど)
- 商品名・色・文字の大きさ・写真・キャッチコピーなどをチェック
- どこが似ていて、どこが違ったかを表にする
- 自分が「一番買いたい!」と思ったパッケージを選び、その理由を書く
マーケティングやデザインに触れるきっかけにもなるので、「将来デザイナーになりたい!」なんて夢を持ってる子にもぴったりの研究です♪
③ ことばのふしぎ研究(早口ことば・漢字・ことわざ)
言葉の世界にも、楽しくて奥が深い自由研究のテーマがたくさんあります。
中でもおすすめは、「ことば遊び」や「日本語の不思議」を調べてまとめること。
✅ テーマ例
- 日本一長い早口ことばを集めて、どこが言いにくいのか考察
- 同じ読み方で意味がちがう言葉(例:「はし」=橋・箸・端)を調べてイラスト付きで紹介
- ことわざや慣用句の「使い方クイズ」を自作してみる
✅ 進め方
- ネットや辞書を使って例を集める
- ジャンルごとに分類(おもしろ系・むずかしい系など)
- 気になったものの意味や使い方を調べて、自分の言葉で説明
- 最後に「お気に入りベスト3」などまとめを入れるとGOOD!
国語好きな子・本が好きな子にぴったりな“知的テーマ”として、先生ウケも◎です!
④ スポーツ選手の出身地マップを作ろう
野球・サッカー・バスケなどのプロスポーツ選手は、日本のどこから多く出ているのか?
そんな視点で「出身地マップ」を作ってみる自由研究も面白いですよ♪
✅ 進め方
- 好きなスポーツの選手を10人くらいピックアップ(ネット検索OK)
- 出身都道府県を調べて一覧表に
- 地図に印をつけて、どこが多いかを視覚化
- 「なぜこの地域が多いのか?」を自分なりに考察
例:「北海道出身のスピードスケート選手が多いのは雪が多いからかも?」など
社会+スポーツの知識+データ整理力がバランスよく求められるテーマなので、自由研究としても完成度が高く見えます!
⑤ 1週間で使った電気スイッチ調べ
家の中で1週間、何回くらい電気のスイッチを入れたり切ったりしているか?を記録してみる自由研究です。
「使ったことを記録するだけ」なのに、省エネ意識や生活の見直しにもつながる素敵なテーマ!
✅ 進め方
- 家族の協力を得て、1日だけでも「何回どこで電気をつけたか」をチェック
- 1週間分のデータを表に記録
- 「いちばん使った部屋は?」「つけっぱなしは何分?」などを分析
- グラフにまとめて、気づいたことや反省点を書く
例:「夜はリビングが多かった」「寝る前に廊下の電気がつけっぱなしだったことに気づいた」など
“自分の生活を研究対象にする”という視点がユニークで、生活科・家庭科にもつながるおすすめテーマです。
⑥ 都道府県の名前に入っている漢字ベスト10
地図や社会の勉強にもつながる、漢字に注目したおもしろテーマ。
47都道府県の名前に使われている漢字を調べて、「いちばん多く使われている漢字ベスト10」をランキングにしてみましょう!
✅ 進め方
- 47都道府県すべての名前をノートに書き出す
- 漢字ごとに回数を数える(例:「山」「川」「田」など)
- ランキング表やグラフをつくる
- 「なぜこの漢字が多いのか?」を自分で考えてみる
例:「“山”は山が多い地域に多いから?」「“田”は農業がさかんな県に多い?」
漢字×地理×考察という3要素が揃っていて、社会科好きな子にぴったりです♪
⑦ 自分の「やる気スイッチ」はどこにある?実録ノート
ちょっとユニークだけど、心の動きを観察する“自己研究”タイプの自由研究です。
毎日、自分のやる気が出た時間・出なかった時間を記録して、「やる気スイッチの正体」を探ってみましょう!
✅ 進め方
- 1日2回、朝と夜に「やる気があった/なかった」ことをメモ
- 1週間分を記録して、共通点を探す
- 「音楽を聞いたら集中できた」「暑いとやる気が出なかった」などをまとめる
- 自分に合う工夫を考えて、来週試してみる!
自分を知ること=立派な研究です。
「やる気が出る工夫ベスト3」「自分の集中力が上がる時間帯」などをまとめれば、将来にも役立つ内容になりますよ✨
⑧ 身の回りのQRコード大調査
いまやどこにでもあるQRコード。ポスター、パッケージ、レシート…
でも、「どんなところに多いの?」「何につながるの?」まで気にして見ている人は少ないかもしれません。
そんな視点から、QRコードを集めて調べてみる自由研究もユニークです!
✅ 進め方
- 1週間、家の中やお店でもらったものからQRコードを集める
- どんな物にあった?(チラシ/お菓子/スーパーのレシート etc)
- スキャンして、どこにリンクされているかを調べて記録
- 表やグラフにして「いちばん多かったジャンル」などをまとめる
例:「10個中、6個は商品紹介ページだった」「クーポンがついているものが3つあった」など
身近な“当たり前”を調べる力=現代的なリテラシーにもつながります♪
⑨ ペットボトルのラベル徹底比較!
同じように見えるペットボトルの飲み物でも、ラベルには違いがたくさんあります!
商品名の書き方やデザイン、原材料、キャッチコピーなどを比べてみましょう。
✅ 進め方
- 3〜5本のペットボトルを用意(お茶/ジュース/水など)
- ラベルに書かれている情報を表にまとめる
(例:原材料、カロリー、保存方法、色・フォント など) - 見た目の印象・買いたくなるデザインなどを自分で評価
- 一番「伝わりやすかった」ラベルを選んで、理由を書く
マーケティング×観察×考察がセットになった、じつはハイレベルな自由研究になりますよ!
⑩ 道路標識の意味を調べてイラスト図鑑に
毎日目にしている道路標識。でも、それぞれの意味や違い、どこに使われるかをきちんと知ってる人は少ないかも?
だからこそ、身近でありながら奥が深いテーマとしておすすめです!
✅ 進め方
- 通学路や近所の道路で、気になる標識を写真 or イラストで記録
- 「止まれ」「通行禁止」など意味を調べる
- 種類別に分類(注意/禁止/案内 など)
- 自分なりの「マイ道路標識図鑑」としてまとめる
追加アイデア:「もし新しい標識を作るなら?」というオリジナル案を入れてもGOOD!
社会・交通安全・創造力が組み合わさった、高学年らしい考察型自由研究になります♪
よくある質問ととこたえ(FAQ)
まとめ:考えて伝える力も立派な“研究”!
「自由研究=実験や工作じゃなきゃダメ?」
そんな心配はいりません!
高学年にとって本当に大切なのは、“興味を持ち、自分で考えて、まとめる力”なんです。
今回ご紹介したテーマは、すべて:
✅ 家の中やネットで調べられる
✅ 道具いらず・親のサポート最小限でOK
✅ 「考える力」と「伝える力」が自然と育つ
とっておきの内容ばかりです。
もし「理科苦手…」「美術も得意じゃない…」と感じていたら、今回のような“調べる・分類する・言葉でまとめる”自由研究にぜひチャレンジしてみてくださいね✨