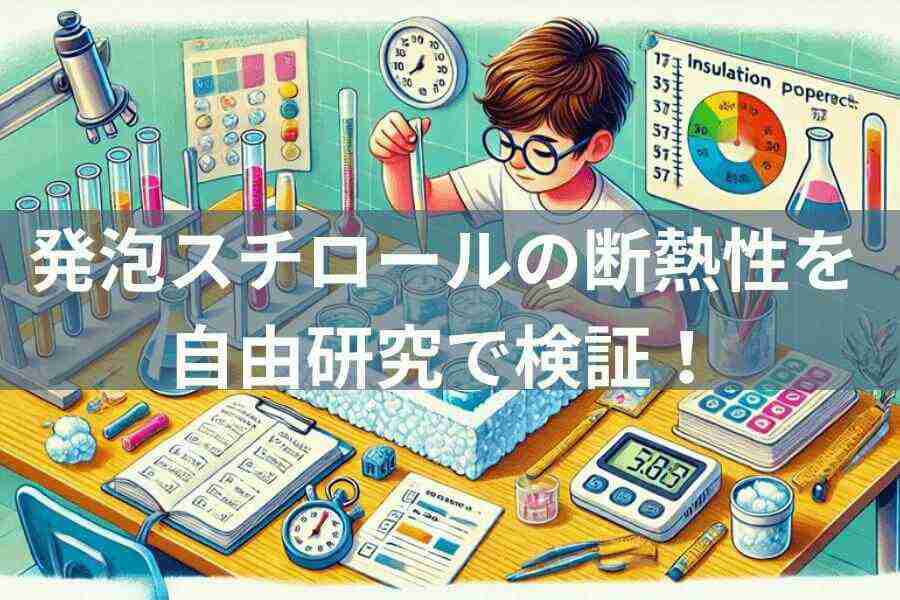身の回りにたくさん使われている発泡スチロール。お弁当の容器や冷たいものを包む箱など、なぜか“温度を保つ”場面でよく見かけますよね。
実はこの素材には「断熱性」という、熱を通しにくい性質があるからなんです。
今回は、そんな発泡スチロールの断熱性を実験で確かめてみる自由研究をご紹介します。
小学生高学年向けに、温度変化の記録方法やグラフの作り方、考察のまとめ方まで、自由研究として評価されやすい構成で解説していきます!
この記事でわかること
- 発泡スチロールの断熱性って何?
- 自由研究に使える実験テーマとしての魅力
- 実際に行う実験の手順と準備物
- 温度の記録方法とデータのまとめ方
- 自由研究にふさわしい考察の書き方
- 実際にやった子どもの感想や注意点
発泡スチロールの断熱性とは?
発泡スチロールは、私たちの身の回りでよく使われている素材です。お弁当の容器、保冷バッグ、冷蔵配送の箱などでよく見かけますよね。
この素材には、「断熱性」=熱を通しにくい性質があり、冷たいものや温かいものの温度を長時間保つために使われています。
どうして断熱性があるの?
発泡スチロールの中には、たくさんの空気を含んだ小さな泡が集まっています。
この空気の層が、外の熱が中に入りにくい&中の熱が外に逃げにくい仕組みになっているのです。
この実験では、その“熱の伝わりにくさ”を実際に自分で確かめてみることができますよ!
なぜ自由研究に向いているの?
断熱性の実験は、小学生高学年の自由研究にとてもおすすめです。その理由は、次のようなポイントにあります。
自由研究にピッタリな理由
- 身近な素材で手軽にできる
→ 発泡スチロール容器は家庭や100均で簡単に入手可能です。 - 実験→データ収集→グラフ化→考察まで一通りできる
→ 高学年らしい“まとめ力”や“思考力”をアピールできます。 - 比較や応用も組み合わせやすい
→ 他の素材(紙・プラスチックなど)と比較すれば、より深い内容に!
「本格的に見えるのに、準備もカンタン」なテーマなので、取り組みやすく完成度も高く仕上がる、まさに自由研究向けの実験なんです♪
実験の目的とねらいを決めよう
自由研究では、“何のためにやるのか”という目的をはっきりさせておくことがとても大切です。
発泡スチロールの断熱性を調べる今回のテーマでも、目的とねらいを自分の言葉で書くことで、より研究らしくなります。
書き方の例(子ども向け)
- 目的:
「発泡スチロールがどれくらい温度を保てるのかを調べてみたいと思った。」 - ねらい:
「冷たい水や温かい水を入れて、時間がたったときの温度の変化を記録して、発泡スチロールの効果を確かめる。」
このように書き出すことで、研究の“出発点”が明確になり、先生にも伝わりやすくなります。
実験の準備:必要な材料と道具
まずは実験を行うための準備をしましょう。材料はほとんどが家にあるものでOK。もし足りなければ、100均で揃うものばかりなので安心です♪
必要なものリスト
- 発泡スチロール容器(食品トレーや保冷用の箱など)
- 紙コップやプラスチック容器(比較対象用)
- 水(冷たい水・お湯の両方を使う)
- 温度計(1〜2本。できればデジタルが便利)
- ストップウォッチまたはタイマー
- 記録用ノート or 自由研究ワークシート
- ペン、定規、色ペン(グラフ作成用)
もし温度計が2本あれば、同時に2種類の容器で比較できるのでおすすめです!1本でもOKですが、その場合は順番に測る工夫をしましょう。
実験方法①:冷たい水の温度変化を調べる
ここから実験スタートです!まずは冷たい水を使った断熱性のテストをしてみましょう。
実験手順
- 発泡スチロール容器に冷水(5〜10℃)を入れる
- 同量の冷水を、紙コップやプラスチック容器にも入れる(比較用)
- それぞれに温度計を入れて、スタート時の温度を記録
- 室温で放置し、5分おきに温度を記録(30分〜1時間)
- 温度変化を表にまとめる(のちほどグラフに)
✅ ここがポイント!
- 室温はなるべく一定に(直射日光の当たらない場所で)
- 容器のふたをしないことで、より分かりやすい結果が出ます
- 測定のたびにしっかり記録を残しましょう!
冷水の温度がどれくらいキープされるかを見ることで、“冷たいものを冷たいまま保つ”発泡スチロールの力が見えてきます♪
実験方法②:温かい水の温度変化を調べる
次に、同じ方法で温かい水を使った実験も行います。
こちらは、発泡スチロールが“あたたかさを逃がしにくい”かどうかを調べるテストです。
実験手順
- 発泡スチロール容器にお湯(約50〜60℃)を入れる
- 同量のお湯を比較用の容器にも入れる
- それぞれの温度を記録し、5分おきに測定(30〜60分)
- 温度がどれくらい下がったかを比べる
※ヤケドに注意し、大人と一緒にお湯を扱いましょう!
✅ ポイント
- 温度が高すぎると危険なので、50〜60℃程度を目安に
- 実験前に容器を水ですすいで“予熱”すると、より正確な結果に
- 測定中は容器を揺らさず、同じ位置に置いておくと◎
この2つの実験を比べることで、発泡スチロールの“断熱性のすごさ”がぐっと理解できます!
データの記録とグラフ化のポイント
実験で記録した温度の変化を、表やグラフにまとめると、とても分かりやすくなります。
高学年の自由研究では、この「見える化」が評価ポイントになるので、しっかりまとめていきましょう!
記録表のつくり方(例)
| 測定時間 | 発泡スチロール容器(℃) | 紙コップ(℃) | プラ容器(℃) |
|---|---|---|---|
| 0分 | 60 | 60 | 60 |
| 5分 | 58 | 55 | 53 |
| 10分 | 56 | 51 | 48 |
| … | … | … | … |
時間ごとの温度を1つの表に並べることで、比較がしやすくなります。
グラフのポイント
- 横軸に「時間」、縦軸に「温度」を取る
- 色分けして、各素材の温度変化を線グラフで表示
- グラフのタイトルや凡例(どの線がどの素材か)も忘れずに!
表 → グラフ → 気づきメモという流れでまとめると、とても見栄えが良くなりますよ♪
他の素材と比較してみよう(紙・布・プラ)
発泡スチロールだけで終わらせるのではなく、「他の素材との比較」をすることで、研究の深みが一気にアップします。
比較する素材の例
- 紙コップ(紙製)
- プラスチック容器(お弁当のタッパーなど)
- タオルや布(包むパターン)
- ステンレスカップ(意外と熱が逃げやすいことも!)
どの素材が一番保温・保冷効果があるかを比較することで、「なぜ発泡スチロールが使われるのか?」がはっきり見えてきます。
比較を入れると「調べる力+考える力」が見えるため、高学年らしい自由研究としての評価がグンと高まりますよ✨
実験結果からわかることをまとめよう
実験の結果が出たら、次はその「データから読み取れること」を自分の言葉でまとめていきましょう。
✅ 書き方のヒント
- 「発泡スチロールは他の素材よりも温度が下がりにくかった」
- 「紙やプラに比べて、熱を伝えにくいことがわかった」
- 「冷たい水でも温かい水でも、断熱性があるのは同じだった」
- 「だから、発泡スチロールは冷蔵の箱やお弁当箱に使われているんだと思う」
難しい言葉や長い説明はいりません。自分の感じたことを、自分の言葉でまとめることが大切です!
考察を書くときのポイント(高学年向け)
自由研究の仕上げとして大切なのが「考察(かんさつ+考え)」のパートです。
実験結果をただ並べるだけではなく、そこから何がわかったのか・なぜそうなったのかを自分なりに説明することで、研究としての深みが出ます。
✅ 考察の書き方のコツ
- 実験結果を一言でまとめる
例:「発泡スチロールは、他の素材よりも熱を通しにくかった。」 - なぜそうなったかを考える
例:「中に空気の層があるから、熱が伝わりにくいのだと思う。」 - 日常生活と結びつける
例:「だから冷凍食品の箱や、お弁当の容器に使われているんだと思った。」 - 次にやってみたいことを書くのも◎
例:「お菓子の箱の断熱性も調べてみたい。」「雪の日にも試してみたい。」
“正しい答え”を書く必要はありません。自分で気づいたこと・感じたことを、しっかり言葉にすることが、自由研究としてとても評価されますよ♪
写真・図を使って見やすくまとめよう
研究内容がどんなに良くても、まとめ方がごちゃごちゃしていたらもったいないですよね。
特に高学年では「見やすさ」や「伝わりやすさ」もポイントになります!
✅ まとめを工夫するテクニック
- 実験風景や温度計の写真を使う
→ ビフォー/途中経過/完成の3点があると◎ - 図やイラストで補足説明
→ 実験の配置、容器の構造などを図にすると一目で分かる - 文字のサイズや色を工夫
→ タイトルは太め、結果は色付き、グラフはカラフルに♪ - まとめシートに整理する
→ 画用紙1枚でまとめてもOK。スライド形式も高評価♪
見た人が「へぇ~!」と感じるような、伝わる自由研究を目指しましょう!
実際にやってみた体験談と感想
このテーマは実際に取り組んだ子どもたちにも大人気!
「身近な素材なのに、ちゃんとした“研究っぽさ”がある」と好評です♪
✅ 体験者の声
- 「最初はめんどくさそうだったけど、温度が変わっていくのを見るのが面白くて最後までやれた!」(小6 男の子)
- 「数字がずらっと並ぶのがかっこよくて、グラフをがんばって書いた!」(小5 女の子)
- 「親子で一緒にやれて、自由研究がコミュニケーションの時間にもなった」(保護者)
- 「実験っぽくて、理科の授業みたいで楽しかった!」(小6 男の子)
やってみると「科学って身近にあるんだ」と感じられる、理科好きへの第一歩になる研究なんですよ♡
よくある質問とこたえ(FAQ)
まとめ:発泡スチロールが使われる理由を自分で実感!
発泡スチロールは、ただの“軽い白い箱”じゃなかった!
冷たいものを冷たく、温かいものを温かく保つ力=断熱性がしっかりあることが、実験を通してはっきりとわかりました。
この研究を通して、お子さん自身が「なんでこれが使われているのか?」という疑問に自分で答えを出せたことが、なによりの学びの成果です。
そして、数字を記録してグラフにしたり、比較を考察したりと、高学年らしい“考える力”も自然に身につけられたはずです。
今年の自由研究は、「楽しかった!」だけじゃなく「わかった!」も一緒に味わえる内容にしませんか?
記事のまとめ
- 発泡スチロールには、熱を通しにくい“断熱性”がある
- 実験によってその性質を自分で確かめることができる
- 冷水・お湯の両方で比較することで理解が深まる
- 他の素材(紙や布)との比較で、断熱性の違いがよくわかる
- 表やグラフでデータを“見える化”すると自由研究らしくなる
- 自分の言葉で考察を書くと、研究の完成度がぐっとアップする